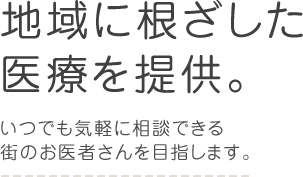仲間の医師と協力して
専門性の高い医療を提供します。
お知らせ 一覧はこちら
- 2024年4月15日
- 求人募集のお知らせ
- 2024年4月11日
- ゴールデンウィークのお知らせ
- 2023年3月31日
- プラセンタサプリ(医療機関専売)の発売を開始いたしました❣
- 2023年3月14日
- プラセンタ注射値下げいたしました!
- 2023年1月28日
- 生プラセンタクリームの販売を開始いたしました!
どんなささいなことでも気軽に相談できる
アットホームなクリニックにしていきます。
大病院の3時間待ちの3分診療ではなく患者さんの立場で親身になり、
共に笑い、時には共に泣けるような医療の原点を目指します。